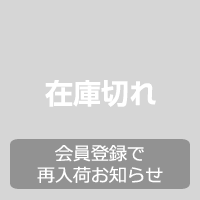黒色火薬の発見
古代から中世まで、永遠の生命や、人工的な金の生成が熱心に探求され、錬金術と呼ばれる、これら初期の科学実験は、実は軍事史にも深く関連している。

By: Daniel Garcia
7世紀に興った北東アジアの唐で、不老不死の万能薬として煉丹が研究されていた。
当時の文献に、全く意図しなかった薬剤ができてしまった失敗例が紹介されている。
硫黄と鶏冠石(砒素)、硝石などを混ぜたところ、不思議な炎が出て、煉丹術師はひどく火傷し、その家屋まで全焼してしてしまった。
だから、「硝石と硫黄に木炭を混合してはならない。」、かように、大いなる災禍に見舞われるだろうと。
言うまでもない、火薬の発見である。
一般に、ヨーロッパに火薬が伝播したのは、早くとも11世紀とされるので、400年も早いことになる。
手榴弾の開発
この黒色火薬は、すぐに軍事兵器に利用され、震天雷として実用化した。
これは、火薬を詰めた陶器を敵陣に投げ込む、手榴弾のプロトタイプと考えられている。
バリエーションとして、火薬とハチミツを混ぜ、ペースト状にしたものを矢尻に塗り、火を付けて発射する火槍(かそう)にも転用。
但し、火薬だけでは爆発力に乏しく、この時期はまだ、敵に大きな損害を与えるには至っていなかった。
恐らくは、ただ爆音で相手を委縮させたり、未知の新規な攻撃で狼狽させるなど、デモンストレーションとしての域を越えなかっただろう。
13世紀のモンゴル帝国から分岐したオゴタイ・ハン国が経験した、防具に用いた厚い牛皮を貫くほどの強力な武器も報告されている。
これも、火薬を詰めた筒に導火線が付いた、手榴弾に似たものと考えられている。
更に、同時期のエジプトを支配したマムルーク朝では、火薬を詰めた壷に、一束の矢を差し込んで封印し、底から伸ばした導火線に火を着けると破裂、何十もの矢を一挙に発射する装置も考案されている。
このように東から西へ、火薬は伝わったと考えられよう。
異説を付記しておくと、8世紀の東ローマには既に、ギリシアの火と呼ばれる兵器、もしくは火薬があったとされるが、はっきりしないが、震天雷と同じく、陶とガラス製の容器に火薬を詰めたもので、投擲用だったと推測されている。
ヨーロッパでは、15世紀にも同様の火薬兵器の存在が伝えられるが、史実として明確なのは、17世紀のザクロと呼ばれた手榴弾だろう。
フランスで開発された手榴弾は、果物のザクロに似たフォルムで、中に火薬を詰めた鋳物製の球体である。
やはり、導火線が付いていて、着火してから敵陣に投げ入れる必要があった。
従って、できるだけ敵側に接近しなければならず、しかも、投擲の技術と体力も不可欠で、しかも、導火線の長さを調節しないと、敵から投げ返されたり、また自陣で爆発してしまう、未だに不安定な製品しかなかった。
ここから、手榴弾攻撃に特化した投擲兵は育成されることになる。
手榴弾(レプリカ)の売れ筋ランキング
投擲兵の設置
1667年、ルイ14世の治世に陸軍中佐マルティネが専門中隊を建議、ルイ15世の下で投擲兵中隊が設置された。
面白いことに、外見からも威嚇せんと試みて、容貌魁偉な巨漢を多く配した上、顎にはヒゲをたくわえさせたという。
わざわざ先の尖った軍帽をも誂えたりしたが、これは身長を高く見せようとしたギミックだった。

By: The U.S. Army
危険を顧みずに、最前線で任務を遂行する投擲兵は、何より勇敢でなければならなかった。
軍制改革に務め軍人王の異名を取った、17世紀前半のプロシャ王・フリードリッヒ1世の時代にあった擲兵部隊は、豪胆な怪力の持ち主ばかりを集めて組織されたという。
英国でも、投擲兵は、王の護衛まで任されるほどの信任厚い存在だった。
1646年、清教徒革命の結果、チャールズ1世が処刑、弟の、後のチャールズ2世は亡命を余儀なくされる。
この時、王(スコットランド王として戴冠)の近衞兵に取り立てられたのが、投擲兵だったのだ。
革命は失敗して王政復古、ロンドンに入城、めでたく英国王位を襲いだ暁には、ロード・ウェントワース連隊として、後に近衛歩兵第一連隊に組み込まれる栄誉を得ている。
ちなみに、近衛歩兵第一連隊は以後の対外戦争にはほとんど参加したとされ、その活躍は、フセイン討伐を目的とした2003年のイラク戦争にまで及ぶ。
近代的な投擲弾の誕生は、20世紀まで待たねばならなかった。
背景には、19世期末、ノーベルによるダイナマイトの発明がある。
ニトログリセリンを素材としたこの新型火薬は、抜群の爆発力に富み、これまでの問題を一挙に解決したと言っても良い。
それまでの手榴弾は爆発力が弱く、兵器や施設に決定的な打撃を与えるには至らなかったのだ。
ミルズ式手榴弾
1915年、更に画期的な兵器が開発される。
ゴルフクラブのデザイナーだったウィリアムズ・ミルズが考案した、スプリングで信管を打撃して着火する新型手榴弾である。
レモン大、570グラムの手榴弾のピンをはずして投げるだけ簡便さゆえに、兵士の訓練も特に必要なかった。

By: David Moss
周囲には48の正方形状のレリーフが刻み込まれて、これは破片が細かく砕かれて四散するように考えられていた。
この先例は、先のノーベルも機雷設置を手掛けたクリミアで、英軍が火薬に曲げた釘を混ぜて作った手製爆弾にも求められるのかもしれない。
ミルズ式手榴弾は、アタッチメントを装着すれば小銃からも発射可能。
何しろ、火薬の性能が向上したために、想定された被害範囲は直径10キロにも及び、当時は塹壕を舞台に展開される攻防が、戦局の進捗を大きく左右した。
野戦での仮設坑路に過ぎなかった塹壕から、機関銃や鉄条網と併用することで、縦深化した塹壕陣地が設けられるようになる。
1899年のボーア戦争が最初だろう。
このような状況で改めて、手榴弾が重要視されるようになったのだ。
第一次対戦では、連合軍が生産したミルズ式手榴弾は7000万発を越えたとも、また、オーストラリア兵は一人で7個もベルトに付け、しかもこれは標準装備だったという。
ただ開戦時、ドイツは7万の手榴弾を備蓄してゐた一方、イギリス軍側は極めて不足していて、ジャムの空き缶に導火線を付けただけの、あり合せの爆弾で急場を凌いだとも伝えられる。
日本の手榴弾
最後に、わが帝国陸軍に目を向けてみよう。
明治時代の手榴弾は、花火と揶揄されるほどに非力で、兵士に配られた手榴弾も、実際には使われずに、戦場に放棄して来てしまった例さえあったという。

By: Julian Carvajal
帝国陸軍では、戦車による機械化と浸透戦術による攻撃を推進していた。
浸透戦術とは、第一次大戦のドイツが得意とした、小隊規模の突撃隊が奇襲突撃する戦法である。
それまでは、密集隊形の前面と側面に、部隊の一部を間隔を置いて散開させ、散兵線を敷くのが歩兵戦術の基本だったが、帝国陸軍は、この浸透作戦を導入する。
これに伴ない、手榴弾が多用されたが、ドイツで投擲兵を設けたのとは異なり、一般の歩兵が投擲の任務もこなし、専門兵科は置かなかった。
一方で、建造物や広い範囲に損害を及ぼす目的から、大型の破壊筒も用いられるようになって行く。
日露戦争後の地雷除去に使われた簡易な爆弾が転用されたのが破壊筒であり、第一次大戦では、突撃の前段階として、鉄条網の爆破に用いられた。
1,5メートルの長さがあり、末尾に信管を差し込み、導火線を繋いで使用した。
破壊筒はその本体を敵陣の中に設置しなければならず、兵士数名が班を構成し、敵陣まで運ぶ必要があった。
1932年2月の第一次上海事変、廟行鎭で武勲を上げたのが、映画や歌舞伎にも組まれ、軍歌も作曲された有名な爆弾三勇士である。
独立工兵第18大隊の江下武二、北川丞(すすむ)、作江伊之助の三烈士は、点火した破壊筒を抱えて、敵陣に向ったのである。
但し、導火線を短く切ってしまったがゆえに、事前に点火せざるを得なかったのが真相のようでもあり、帰還のかなわない特攻作戦などではなかったと見るべきだろう。